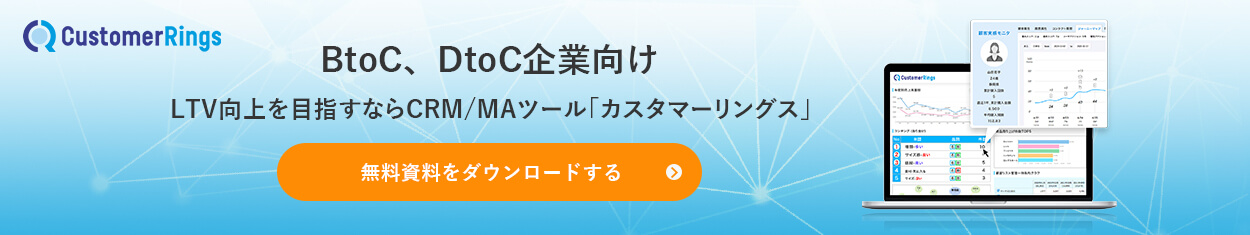数年前からオンラインと実店舗の両方を活用していく局面においてよく聞かれるようになったキーワードに、O2Oやオムニチャネルなどがある。2017年には、こうした施策から一歩進んだ「OMO」という言葉が中国で誕生し、以後、アメリカや日本でも認知を広げている。今回は、このOMOについて理解を深めていこう。
目次
OMO(Online Merges with Offline)とは
OMOが生まれた背景
OMO、オムニチャネル、O2Oの違い
OMOに取り組むメリット
OMOをマーケティングで活用する際の考え方
マーケティングや店舗でOMOを成功させるポイント
OMOの普及がもたらす未来
OMO事例
まとめ
OMO(Online Merges with Offline)とは
OMOは「Online Merges with Offline(読み方:オンライン マージズ ウィズ オフライン)」の略称で、オンラインとオフラインの融合を意味する。元Google Chinaのトップであり、シノベーション・ベンチャーズ創業者である李開復(リ・カイフ)が提唱し、2017年12月にザ・エコノミスト誌に発表されたことによって広まった言葉だ。中国は世界的に見てもIT化が進んでおり、デジタルが国民の生活に浸透している国である。スマートフォンの普及率が非常に高く、モバイル決済が主流のため、スマートフォンがあればオンライン・オフラインの区別なく買い物を楽しむことができる。
そんな中国で誕生したOMOは、O2Oやオムニチャネルのようにオンラインとオフラインを独立したものとして運用するのではなく、オンラインとオフラインを連携させてマーケティング施策を行うものである。それぞれのチャネルを総合的に考えることで、「顧客目線」に沿ったシームレスな顧客体験を提供することが可能に。オン、オフの垣根をなくし、適切なタイミングで適切なチャネルを提供するOMOは、よりよい顧客体験の提供につながると考えられている。
OMOが生まれた背景
昨今ではスマートフォン等を使ったウェブサービスが充実しており、顧客はものを買うたくさんの手段を持つようになった。つまり顧客は、利用したいと思った瞬間に最も便利なサービスを選ぶということ。この際に、オンラインかオフラインかという視点は、顧客にとってはあまり関係がなく、企業目線での視点だといえるだろう。
例えば中国のOMO先進企業のひとつであるビットオート(易車)は、カーライフサイクルという顧客視点の概念を提唱している。顧客が免許を取得してから新しい車に買い替えるまでのサイクルを効率化するために多くの企業に対して連携や投資を行っているが、ここで重要視しているのが、オンラインとオフラインを分断しないOMOの考え方なのだという。
最近日本で問題となっているのが、実店舗に訪れてもその場では購入せず、Amazonや楽天市場などの大手総合ECサイトで購入する“ショールーミング”という現象だ。実店舗がショールームのように扱われてしまい、自社の売り上げにつながらないという状況である。
自社の売り上げを伸ばすためにはOMOの施策が必要であり、OMOにつながる施策としてO2Oやオムニチャネルがある。オンラインとオフラインを分断する考え方では顧客を逃してしまうため、顧客のニーズに合わせて、オンラインとオフラインの両方を考慮したサービス展開が必要になってくるのである。
OMO、オムニチャネル、O2Oの違い
ここで一度、O2Oとオムニチャネルについて整理しよう。
O2Oとは「Online to Offline」の略で、インターネット上(オンライン)からリアル店舗(オフライン)への集客や購買行動へと促す戦略のことである。場合によっては、その逆のオフラインからオンラインへと誘導する施策を指すこともある。具体的には、ECサイト上で実店舗の割引クーポンを配布したり、スマホのGPS機能を利用してクーポンを配信したりといった施策が挙げられる。
オムニチャネルとは、実店舗、ECサイト、カタログ通販、ソーシャルメディアなどの複数のチャネルをシームレスに連携させ、「いつでも、どこでも同じように利用できる」形を作ることでユーザーにアプローチする戦略のこと。店舗に商品の在庫がなくてもECから購入できたり、受け取りは最寄りの店舗でできたりと、ユーザーが欲しい商品を好きな時に、好きな場所で受け取れるようにする施策を指す。
このように、これまではオンラインとオフラインとを分けて考えており、この2つの間をどう顧客に行き来してもらうかという視点での施策が中心であった。
これに対してOMOは、オンラインとオフラインを融合させるという考え方である点が大きな違いである。
OMOに取り組むメリット
オンラインとオフラインを融合させてシームレスな購買体験を可能にするOMOは、企業に次のようなメリットをもたらす。
1.機会損失の防止
顧客がどのチャネルでも好きなタイミングで購買できるようになり、在庫情報の一元化も可能になるため、販売機会の損失を防止できる。
2.体験価値の向上
顧客データをオンライン・オフラインの区別なく統合管理することで、顧客一人ひとりのニーズに合わせた体験価値を提供できるようになる。
3.LTVの最大化
よりよい顧客体験の提供がファン化の促進につながるほか、顧客データを活用した効果的なリピート施策を実施することで、LTVを最大化できる。
OMOをマーケティングで活用する際の考え方
顧客は、スマホやPCでどこにいてもオンラインに接続することが可能なだけでなく、店頭でもPOSシステムなどを経由してその行動履歴が、個人と紐付けられる状況にある。このように、常に企業のタッチポイントと接触している環境を前提とした施策を打ちだすことが、OMOの基本である。
これまで日本の多くの企業は、オフライン(実店舗)を土台にオンラインサービスを付随させるという試みを行ってきた。それに対し、OMOはオンラインを土台とした考え方であるため、オフラインについては顧客と接点が持てる貴重な場として捉える必要がある。単にオンラインとオフラインを融合させるのではなく、どちらを土台と考えるかによって、マーケティング施策は変わってくるのである。
マーケティングや店舗でOMOを成功させるポイント
OMOは、蓄積した顧客データからニーズを把握し、よりよい顧客体験を提供することが鍵となる。ここでは、様々なデータをマーケティングで活用し成果を上げるためのポイントを解説していく。
1.データベースの整備
OMOはオムニチャネルやO2Oとは根本的に異なる概念のため、まずはデータベースなどのシステム面をあらかじめ整備しておく必要がある。特に顧客データの一元管理は重要な基礎となるので、様々なサービスと連携がしやすい設計を行う。既存の顧客データが複数存在するケースも少なくないため、それらをどのように紐付けてどのように活用するかも考慮しよう。また、OMOでは顧客データの価値が高まるため、セキュリティ対策も非常に重要である。不正対策や情報漏えい防止のほかプライバシーの保護も意識し、顧客が安心して利用できるサービスを心がけたい。
2.データの分析・活用
顧客データや売上データなどのあらゆるデータを分析し、顧客一人ひとりにパーソナライズされた体験価値を提供することが、効果的なOMOマーケティングの実現へとつながる。スマホは今や消費者の生活に欠かせないアイテムであり、なおかつ顧客の行動を把握・分析しやすくなるなど企業側のメリットも大きいため、スマホやアプリを活用したマーケティング施策は一考の価値があるといえる。
3.マルチチャネル化
SNS、メールマガジン、アプリなどの顧客接点を増やせば得られる顧客情報も増え、それらのデータをもとに新たな体験価値を提供しやすくなる。OMOにおいてはスマホが大きな役割を持ち、モバイル決済の利便性に加え店頭受取やモバイルオーダーなどオンラインとオフラインを結ぶ架け橋となるため、スマホを活用したOMO戦略につなげるのも有効だ。
また、OMOを取り入れた「OMO型店舗」においては、データの一元化や分析ツールの導入、販売チャネルの拡大のほか、オンライン決済が基本となるためあらゆる決済システムと連携させることも成功の鍵となる。詳しくは以下の記事で解説しているので、必要に応じて参考にしてほしい。
OMOの普及がもたらす未来
オン、オフの垣根をなくしCXを追求するOMOは、顧客満足度の向上はもちろんのこと、業務の効率化も実現可能だ。顧客データを蓄積・活用しやすい環境が整い適切な施策を立てられる、在庫管理を最適化して機会損失を防ぐなど、売上向上や事業拡大へと繋げるための重要な軸となる。また、OMOを活用した革新的なサービスが今後登場し、マーケティングの幅が広がっていくことも考えられる。
日本は中国やアメリカと比べて導入が遅れていたが、コロナ禍により情勢が変化し、OMOの需要は急速に高まっている。感染防止の観点からもキャッシュレス決済の導入が進み、実店舗が顧客接点としての重要な役割を持つようになった今、日本でもOMOが普及するための土台が整いつつあるといえるだろう。
OMO事例
ここからは、さまざまな企業のOMO施策事例を具体的に見ていきたい。
1.Tencent
OMOは、デジタル先進国である中国で隆盛を極めている。すでに中国では、モバイル決済利用者の買い物や食事、観光などの行動がデータ化され、各々のIDに紐付けされているという。
中国・深セン市に拠点を置くインターネット企業のTencentは、飲食業界のスマート化にも注力。2018年5月には周黒鴨(鴨肉加工食品の小売店)と「WeChatPay」が提携し、スマート店舗が開業した。顧客が初めて来店するときに、チャットアプリ「WeChat」上でアカウントを取得し顔認証を行っておくことで、次回から顔認証のみでの入店が可能に。また、会計の際もセルフレジに商品を置くだけで、搭載されている認証装置カメラで顔認証されると決済が完了する。初回はスマホが必要であるが、2回目以降は、現金やクレジットカードはもちろん、スマホも持たずに購入できるという。
ほかにも、「WeChat」では、駅に設置されているQRコードを読み込むことで発着時刻を教えてくれるミニプログラム「小程序(シャオチェンシュ)」を2017年にリリースしている。これは専用のアプリをインストールしたりダウンロードしたりすることなく利用できるサービスだ。
2.盒馬鮮生(フーマー)
中国Eコマースの大手企業Alibabaが運営する盒馬鮮生は、ニューリテール(新小売)戦略を掲げるネットスーパー。実店舗とECサイトが同期しており店頭とアプリ上の情報が一致するほか、実店舗の商品に貼られたQRコードを読み取ることで産地情報を参照できる。店頭で購入しない場合もQRコードを読み取ってECサイト経由で商品を購入し、自宅まで配送してもらうことが可能だ。
3.株式会社Zoff
メガネの量販店である株式会社Zoffでは、実店舗とECサイトの情報を連携させ、より買いやすいECサイトを展開している。基幹システムと連携し店舗の顧客データをECサイトに紐付けられるようにしており、顧客が自分の度数等を覚えていなくても、ECサイトにログインすれば「度数」「レンズの種類」「以前どの店舗で購入したか」を画像で確認することが可能。メガネは“店舗に行って買うもの”というイメージを打ち破り、オンラインでメガネを購入するという流れを生み出したといえるだろう。
4.LINE株式会社
SNSサービス「LINE」の提供で知られるLINE株式会社は、2019年6月に開催した戦略発表会(LINE CONFERENCE 2019)にて、OMOの概念による「Life on LINE」の実現を目指すことを発表。具体的な戦略の一つに「LINEミニアプリ」がある。
「LINEミニアプリ」は、企業や店舗が、LINEの中にミニアプリを開設できるのが特徴。メニューや利用料金の紹介、予約フォームの設置、クーポンの発行、ポイントカード機能なども用意できるため、消費者の利便性も高まりそうだ。同社の説明によると、たとえばクリーニング店では、会員証やポイントカード、支払い機能を「LINEミニアプリ」が管理し、お預かり完了や仕上がり日のリマインドなどを知らせてくれるなど、顧客の状況に合わせたタイミングでコミュニケーションを図ることが可能とのこと。企業にとっては、独自にアプリを開発する手間を省くことができ、また顧客にとっては、個別にアプリをダウンロードしなくてもLINEの中で全てのサービスとつながることができるため、オンライン・オフラインの垣根なくサービス提供を受けることが可能となるだろう。こちらは2020年春にサービスの提供を開始予定とのこと。
5.Walmart(ウォルマート)
アメリカに本社を持つスーパーマーケットチェーン「Walmart」は、スマホアプリやデリバリーなど複数の領域でOMO戦略を取り入れている。ストアマップ機能は欲しい商品の価格と陳列場所がスマホアプリ上に表示されるというもので、広大な店舗でもスマホ片手に快適なショッピングができる。これにより、イベントなどで陳列場所が変わってもスムーズに目当ての商品を見つけることが可能だ。デリバリーの領域では、ECサイトで注文した商品を実店舗で受け取る「オンライン・グローサリー・ピックアップ(OGP)」というサービスを提供している。OGPが日本で定着している店舗受け取りサービスと異なるのは、パーソナルショッパーという担当者が必要に応じて購入者の希望を聞き、それに応じた商品をピックアップする点だ。ECサイトでありながら商品を手に取るような感覚で買い物ができるほか、商品の受け渡しは実店舗で行われるため、配送にかかる企業側の負担が少なくて済むというメリットもある。
まとめ
OMOとはオンラインとオフラインを分断せず、それぞれの良いところを採用していこうという考え方である。上記の事例からもわかるように、OMOは顧客視点での利便性に優れているだけでなく、企業においても顧客の購買履歴を容易に蓄積できるという大きなメリットがあるのだ。特に日本ではオフラインを土台とした考え方が根強く、OMOに取り組む事業者も大手企業が大半だったが、コロナ禍によるキャッシュレス化の後押しもあり、OMOが普及するための環境は整いつつある。O2OやオムニチャネルもOMO施策の一部と捉えられるが、国内の企業はまだ模索の段階にあるのが現状だ。中国やアメリカを筆頭として世界的にアフターデジタルの概念が急速に広まる中で、OMOを理解しておくことは今後のマーケティング戦略において重要になってくるだろう。