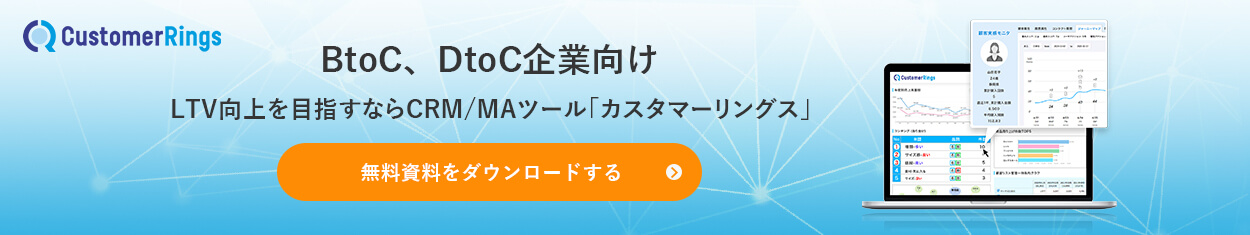OKRとは?背景、メリット、MBO・KPIとの違い、設定方法、運用のポイント

- Writer:
- 山崎雄司
OKRとは、企業や団体の目標と個人の目標を一致させる目標管理のフレームワーク。Objective(目標)、Key Results(主要な成果)の頭文字から「OKR」と呼ばれる。
OKRとは?
OKRはもともと米国intel社から生まれた目標管理の手法で、 GoogleやFacebookのMeta、メルカリなどが導入したことで注目を集めている。企業内の全組織が同じ課題解決に向けて取り組み、メンバー一人ひとりの意欲を向上させながら、組織全体の目標達成を目指す。
OKRが必要とされる背景
多くの組織で採用されている従来型の目標管理システムは、個人に合わせて目標が立てられるため、企業・チーム・個人の目標の方向性にずれが生じる可能性があった。また、従来型のシステムでは、評価の頻度が半年~1年程度と低めであることが一般的。一方、OKRは本質的には個人の意見を取り入れながら経営方針を決定するボトムアップ方式であり、評価も週単位からと、頻度が高い。こうした背景から、昨今のような変化の激しい時代に合ったOKRのフレームワークに注目が集まっている。
OKRの基本事項
Objectiveとは
Objectiveは、言葉通り「目標」を意味する。組織、または個人としてどうなりたいか、何を目指したいかを、シンプルで具体的な言葉で定める。1~3か月間程度の短期間で達成できるものが望ましく、目標の難度は6~7割程度が妥当。
Key Resultsとは
Key Resultは「成果指標」のこと。Objectiveで設定した目標に対して達成すべき計測可能な数値を3~5つ程度設定し、部署やチーム、個人単位で管理する。目標を絞ることで、リソースの分散を防ぎ、集中して達成に向かうことができる。
進捗率
OKRの達成の度合いを0~100%で表す。それぞれの進捗率を1on1ミーティングなどで定期的に確認し、全員が現在の達成状況を定量的に把握する。期間中は、必要に応じて目標をより実態に合ったものに変更することも推奨されている。
自信度
「Key Resultsに対して、達成する自信がどれくらいあるか」を0~10の数字で示すもの。これにより、目標の難易度や達成の見通しを表す。頑張れば達成できるという程度の5~6が妥当で、自信度を共有することで目標達成に向けたメンバー同士の協力が活発化する。
OKRの特徴
高い目標設定
OKRでは、“ノルマを達成するような目標”ではなく、自分たちが達成した姿を魅力に感じるような“挑戦しがいがあり、実現すればインパクトが高い目標” を設定する。この目標は、達成度70%程度でも満足のいくような、従来の手法では達成が困難であるほど高い目標「ムーンショット」を設定。なお、達成率100%を目指すような、頑張れば到達できそうな目標は「ルーフショット」と呼ぶ。
ボトムアップ型の組織をつくる
個々のメンバーの主体的な提案行動が起点となるため、OKRは自律型の組織において効果が得やすい。メンバーがそれぞれの目標や具体的な成果について考え、チームに共有することで、チームの目標の設定に活かされ、組織全体の目標にもつながっていく。
短いサイクルで目標を設定する
基本的に四半期サイクルをベースに検討する。短いサイクルで見直しを行うことで、不透明で変化の速い環境下でも、メンバーから思わぬアイデアが生み出されたり、メンバーの行動が柔軟に変化したりすることも。
OKRのメリット
組織全体で目指す方向が一致
組織全体の目標からチームの目標、個人の目標までを可視化し、フィードバックを頻繁に行うことで、それぞれの目標の方向性を一致させ、団結力の向上を図ることができる。
迅速で柔軟な組織に
OKRを取り入れることで、組織としての目標と個人の目標が都度アップデートされるため、短期間で方向性の見直しが可能に。迅速にPDCAサイクルを回すことで、急激な社会の変化や企業の方針転換にも一人ひとりが柔軟に対応できる。
社内でのコミュニケーションが活性化
OKRが共有されることにより、同じチームの仲間がどのような目標を持つのか可視化され、メンバーの協力体制が構築される。さらに部門を越えた全社的なコミュニケーションの活性化も期待できる。
目標設定が形骸化しにくい
レビューのスケジュールに沿ってOKRの確認、評価を実施し、PDCAを短期間で回す。これにより目標設定の質が高くなり、目標が形骸化しにくくなる。
従業員のエンゲージメントが向上する
メンバーが自発的な目標管理を行うことで、大きな目標に向かい、どう取り組めばいいのか自発的に考える姿勢が醸成される。これにより、メンバー一人ひとりのモチベーションやエンゲージメントの向上につながる。
MBO、KPIとの違い
MBO(目標管理制度)とは
「MBO(Management by Objective)」は「目標による管理」という意味で、現在多くの企業で採用されている手法。一般的に企業の目標に沿って個人やチームで目標を設定し、その達成度を個人で管理する。四半期から半期ごとに目標の達成度を測定し、人事評価に活用される。目標に対して100%の達成度が求められる。
KPI(主要業績評価指標)とは
KPI(Key Performance Indicator)は「主要業績評価指標」という意味で、目標達成までのプロセスを計測する指標のこと。原価や売上など細分化された数値目標を明確化するのに適しており、OKRと併用する企業も。ただし、OKRとは違い、プロセスを確認する指標のため、進捗率は100%が理想である。
OKRの設定方法
OKRを導入する場合、企業の規模にもよるが3か月前には準備を始める企業が多い。組織全体→チーム→個人の順にOKRの設定を行う。それぞれの設定は1か月程度の期間を見込む。
組織の目標(O)を決める
まずは、組織の目標を設定することから始める。「実現可能な目標か」「期限が明確に示されているか」「6~7割程度の達成率が見込めるか」を重視する。
企業の成果指標(KR)を決める
組織で定めた目標を達成するために、必要な指標はどのようなものであるか検討する。指標は目標達成に大きく影響を与えるものを厳選し、3~5つ程度に絞る。
チームや個人のOKRを決める
企業のOKRを基に、チーム、個人の順にOKRを設定する。それぞれの成果指標(KR)も2,3点に絞り、目標に対して6~7割程度で達成できる指標を設定する。
定期的にフィードバックを行う
OKRの設定後は、定期的にミーティングを行い、メンバーの進捗状況を確認する。
OKR運用のポイント
こまめに進捗状況を共有する
週ごと、月ごとに進捗を確認し、組織全体で共有することで、チーム間、また部門を超えたメンバー同士のコミュニケーションの活性化させ、社員同士の団結力を高める。
評価は迅速に行う
OKRでは、週~月単位という短い期間でフィードバックを行うことで、継続的なパフォーマンスを定量的に管理することができる。OKR支援ツールなどを用いて効率化する方法も。
OKR運用の注意点
人事評価と切り離す
OKRは、「生産性の向上やメンバー同士のコミュニケーションの促進」を目標とするため、人事評価や報酬決定のために活用することは推奨されていない。一方で、OKRは評価にまったく反映させてはならないというものではなく、他の評価制度と併用している企業もある。
OKRが適さないケースも
忘れてはならないのが、OKRがすべての組織の目標管理に適しているというわけではないということだ。KPI(重要業績評価指標)のような達成度100%を目指す目標設定が適している場合もあれば、一部の部門のみOKRでの管理が適切というケースも。前述の通り、MBO(目標制度)など他の管理方法と併用して評価を行う場合もあるだろう。